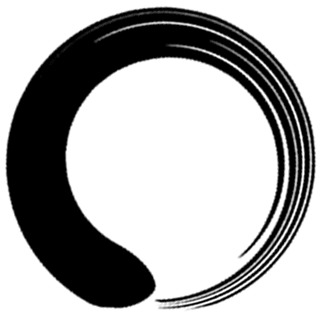
涅槃会
涅槃会は
お釈迦様が入滅された日に
行う法要です
お釈迦様
およそ2500年前に仏教を開かれた
お釈迦様は
悟りを開く前は
(姓)ゴータマ Gautama
(名)シッダッタSiddhattha
と呼ばれていました
悟りを開かれてからは
釈迦族の聖者という意味の
釈迦牟尼(しゃかむに)
悟りを開いた人という意味の
仏陀(ぶっだ)
この世で最も尊い人という意味の
世尊(せそん)
などと呼ばれました
お釈迦様の誕生についての記事
入滅の様子
お釈迦様の入滅の記録が
涅槃経(ねはんぎょう)
という経典にまとめられました
.
涅槃経というお経は 数種類あり
内容が異なります
.
ここでは 初期仏教の
大般涅槃経Mahāparinirvāṇa-sūtraを基に
最後の様子を記します
.
.
.
お釈迦様は
仏教を開かれた後
40年以上に渡り
布教の旅を続けられました
.
毘舎離(ヴァイシャーリー Vaiśālī)で
80という歳を迎えられたとき
入滅を覚えられ
弟子のアーナンダに こう告げました
.
修行を完成した人は
もしも望むなら 寿命のあるかぎり
この世に留まる
あるいは
それ以上に留まることができるだろう
.
つまり
アーナンダよ
貴方が望めば
私の寿命は延びますよ
.
このように述べましたが
この時 アーナンダは
マーラ(魔)に取り憑かれていて
ボーっとしていました
そのため
お釈迦様の延命を願いませんでした
.
アーナンダが その場を去ったとき
マーラ(魔)が姿を表し
すぐに入滅するよう勧めましたが
.
慌てるな
私は3ヶ月後に涅槃に入るだろう
.
このように応えた お釈迦様は
自らの神通力で「命を保つ力」を
捨てさられたのでした
.
.
お釈迦様は
生まれ故郷のカピラ城で
最後を迎えるために
王舎城を後にしました
.
.
パーパーという場所に着いた時
純陀(チュンダ Cunda)から
施食を申し出を受けました
.
この時
お釈迦様は チュンダに言いました
.
チュンダよ
あなたの用意した料理の
スーカラ・マッダヴァ
(sūkara maddava)は
私にだけ給仕するようにし
弟子たちには
別の 硬い食べ物と 柔らかい食べ物を
給仕してください
.
そして
残ったスーカラ・マッダヴァは
穴に埋めるように
.
チュンダよ
神・魔・梵天・修行者・婆羅門の世界や
神ないし人間という生き物の中でも
この料理を食べて
正しく消化できる者を
如来の他に 私は知らない
.
.
ちなみに
このスーカラ・マッダヴァという料理は
キノコ料理とも 豚肉料理とも
言われています
.
.
お釈迦様はスーカラ・マッダヴァを
少しだけ食し 残りを穴に埋めさせ
他の者は 別の料理を食しました
.
その後
お釈迦様は
腹痛と下痢と出血に苦しみながらも
再び旅立ちます
.
.
その道中 アーナンダに
次のような話をしました
.
私の生涯で 二つの優れた供養があった
※スジャーターとチュンダからの供養
.
この二つの供養の食物は
まさに等しい実り
まさに等しい果報がある
.
他の供養の食物よりも
はるかに優れた大いなる果報があり
はるかに優れた大いなる功徳がある
.
これは お釈迦様が
チュンダが後で人々から
責められないようにするため
配慮したモノとされています
.
数多くの涅槃経でも
スジャーターとチュンダの供養は
等しく果報があると記されています
.
.
.最後となる道中でしたが
説法を続けられました
.
クシナガラという地に到着したとき
死期が近いことを悟られ
ヒラヌヤヴァティー河で
最後の沐浴をされました
.
河の畔は娑羅の樹の林でした
2本並んだ娑羅(沙羅双樹)の木下に
頭北 面西 右脇臥
ずほく-めんさい‐うきょうが
つまり
頭を北、顔を西に向け
右脇腹を下にした格好で
横たわりました
.
.
この時
沙羅の樹々が
入滅を告げるために
一斉に花を咲かせて
白い花びらが舞い散った
(或いは 真っ白に枯れた)
という話もあります
.
お釈迦様は
アーナンダ(阿難)尊者に
水が飲みたいことを伝えると
すぐに
アーナンダ(阿難)尊者は
水を汲みに行きましたが
川が濁っており
キレイな水を得られませんでした
.
この事を報告しましたが
お釈迦様は
再度 水が飲みたいと仰ったので
再度 川に行くと
今度は 川が澄んでいて
無事に キレイな水を届けられました
.
この話が
末期の水(死に水)の
由来となりました
.
.
.
最後の説法が
行われます
.
自らを拠り所として
他人を拠り所とするな
法を拠り所として
他のモノを拠り所とするな
(中略)
全ての事象は 移りゆくものである
怠ることなく
修行を続け 完成させよ
.
.
こう告げられた後
お釈迦様は
完全なる涅槃(無余涅槃)に
入られました
.
.
.
ちなみに
自らを 拠り所とせよ
法を拠り所とせよ
.
この「拠り所」のサンスクリット語は
ローマ字表記でdīpaと発音します
島、洲
洪水が起きたときの避難場所
といった意味なので
「拠り所」と訳されます
.
似たような発音の言葉に
明かり、灯明
という言葉があったため
漢訳した人が
自灯明 法灯明と
記したようです
.

涅槃図
この時の様子を描いた仏画を
「涅槃図」と言います
.
.
涅槃図も様々ですが
描かれる事が多いモノを
あげてみます
.
.
◯お釈迦様
中央の宝台に横たわった
お釈迦様は
ひときわ大きく 金色で描かれます
.
.
◯お釈迦様の周りに多くの衆生
弟子や菩薩 天、龍などの八部衆
在家の人から鬼・夜叉
動物 昆虫などが集っています
.
.
◯満月
お釈尊様が入滅された時
満月だったことを表します
.
.
◯二本ずつ四組の沙羅の樹
幾つかのパターンがありますが
3つあげます
.
(パターン1)
八本とも緑
.
(パターン2)
四本は白 残りの四本は緑
お釈迦様が入滅する時
”沙羅の木が白く変色した”
という話が表現されています
.
沙羅の樹が8本 描かれますが
4本は青々と 4本は白く描かれます
.
そして その意味を
白く変色したのを”枯れた”と捉え
お釈迦様の肉体は滅び
沙羅の樹も 枯れた
しかし
お釈迦様の教えは栄えるので
沙羅の木も 青々としている
とします
.
これを四枯四栄と言います
.
.
(パターン3)
八本とも白く描く
沙羅の樹が白くなった
という話を
白い花が咲いた
と表現する場合もあります
.
.
沙羅の樹が白くなったことに
由来するのが
鶴林(かくりん)という言葉です
.
白くなった沙羅の樹が
鶴に見えたことに由来します
.
鶴林という言葉は
やがて 転じて
お釈迦様の入滅を指したり
人が亡くなることを指したりします
更には
お寺や、お寺の樹林のことも
鶴林
と呼ばれるになりました
.
.
◯絵の上部に摩耶夫人
天界から摩耶夫人が駆けつけた様子です
婦人は
もっと生きて衆生を救って欲しいと願い
延命の薬が入った袋を投げた
という話が描かれています
.
この話が
薬を与えることを 投薬と呼ぶ由来です
.
.
◯木に引っかかった薬袋
薬袋は 木に引っかかっています
これは
薬が届かなかったことを
表しています
この時 袋を落とすため
ネズミが 木に登ろうとしました
しかし
猫が ネズミの邪魔をして
薬が届かなかったという話があります
.
そのため
多くの動物が描かれる中
身近な動物にも関わらず
猫は描かれることが 稀です
.
.
◯お釈迦様の足を撫でている老人
お釈迦様が 最後に得度させた人物
須跋陀羅(スバッダラ)です
この時120歳だったと言われています
40年以上の布教活動された釈迦様を
労っています
.
この老人には 別の説もあります
悟りを開く直前に乳粥供養をした
スジャーターだとする説もあります
.
.
◯気絶した人
悲しみのあまり気を失い倒れた人物は
お釈迦様のいとこで 十大弟子の一人
阿難(アーナンダ)尊者です
.
常にお釈迦様に仕え
お釈迦様の言葉を最も多く聞いた
多聞第一と称される人物です
.
容姿端麗、美男子だったと伝わるため
美しい顔立ちで表現されます
.
.
◯アニルッダ(Aniruddha )尊者
(一節では)お釈迦様のいとこで
天眼第一と称される十大弟子の一人です
.
涅槃図の二箇所に 描かれます
一つは
麻耶夫人を先導している姿
(阿那律:あなりつ)
もう一つは
阿難尊者を介抱している姿
(阿泥樓駄:あぬるだった)
悲しむ仏弟子たちを慰めています
.
.
.
◯天龍八部衆
.
帝釈天と配下の四天王
.
龍が巻き付いた2人の人物
八大龍王の長である難陀龍王
その弟の跋難陀龍王
.
鬼神
夜叉
.
獅子などの動物の冠をかぶった人
乾闥婆
.
三面六臂で赤色(青黒色)の鬼神
阿修羅
.
象の冠をかぶった人
緊那羅
.
鳥の冠をかぶった人
迦樓羅
.
蛇の冠をかぶった人
摩睺羅伽
.
.
.
◯その他
.
双髻の童子
迦葉童子
.
医者
耆婆
.
お仁王様
執金剛神と密迹金剛神
.
.
龍が描かれている(供物をもった)人
善女竜王
男神として表現されることも多いのですが
八大龍王の一尊娑伽羅龍王の三女です
.
法華経では8歳の龍女として登場し
一瞬のうちに覚りを得て
成仏された様子が描かれています
.
出家してない在家でも
女性でも
8歳の子供でも
人間でなくても
悟れると
大乗仏教は説いています
.
.
鬼・羅刹
.
様々な動物
ね うし とら う・・・
といった十二支の話があります
しかし
十二支は 古代中国発祥なので
後世の創作かと思われます
.
.
まだまだありますので
機会があれば
各お寺でたずねてみて下さい
.
.
.
仏教三大聖樹
仏教で三大聖樹とされているのは
以下のとおりです
無憂樹(むうじゅ)
阿輪迦の木
摩耶婦人が この木の枝に手を触れて
産気づかれ お釈迦様が誕生したので
.
印度菩提樹(いんどぼだいじゅ)
天竺菩提樹
この木の下で悟りを開かれたので
.
沙羅の樹(さらのき)
沙羅双樹
釈尊が亡くなった場所が
沙羅の樹の林だったので
.
沙羅の樹は
インドの中・北部から
ヒマラヤ地方にかけて
温かい地域で分布しています
.
耐寒性が弱いため
日本で育つのは大変難しい植物です
そのため
日本では
ナツツバキを沙羅双樹と呼んでいます
仏舎利
入滅後
クシナガラを治めていたマルラ国では
お釈迦様を追悼する礼拝が
七日間 行われました
.
お釈迦様の遺体を 火葬(荼毘)した
ラーマバル・ストゥーパ(荼毘塔)が
現在でも クシナガラの郊外に
残っています
.
荼毘(火葬)のあと
お釈迦様と縁のあった諸国で
お釈迦様の遺骨や遺灰は
分与されました
.
.
日本では
名古屋にある覺王山 日泰寺に
お釈迦様の御真骨が祀られています
.
日泰寺は
明治37年(1904)に
釈迦様の御真骨を
奉安するために建立された
日本で唯一の宗派を超えた寺院です
.
下記の写真は日泰寺の仏塔です

卒塔婆(そとば)
.
ストゥーパ(荼毘塔)とは
仏舎利を安置し
供養するための建造物を言います
.
卒塔婆(そとば)
塔婆(とうば)
塔(とう)
などとも呼ばれます
日本で卒塔婆というと
故人を供養するために用いる
木の板を指しますが
卒塔婆は
ストゥーパ(荼毘塔)を模したモノです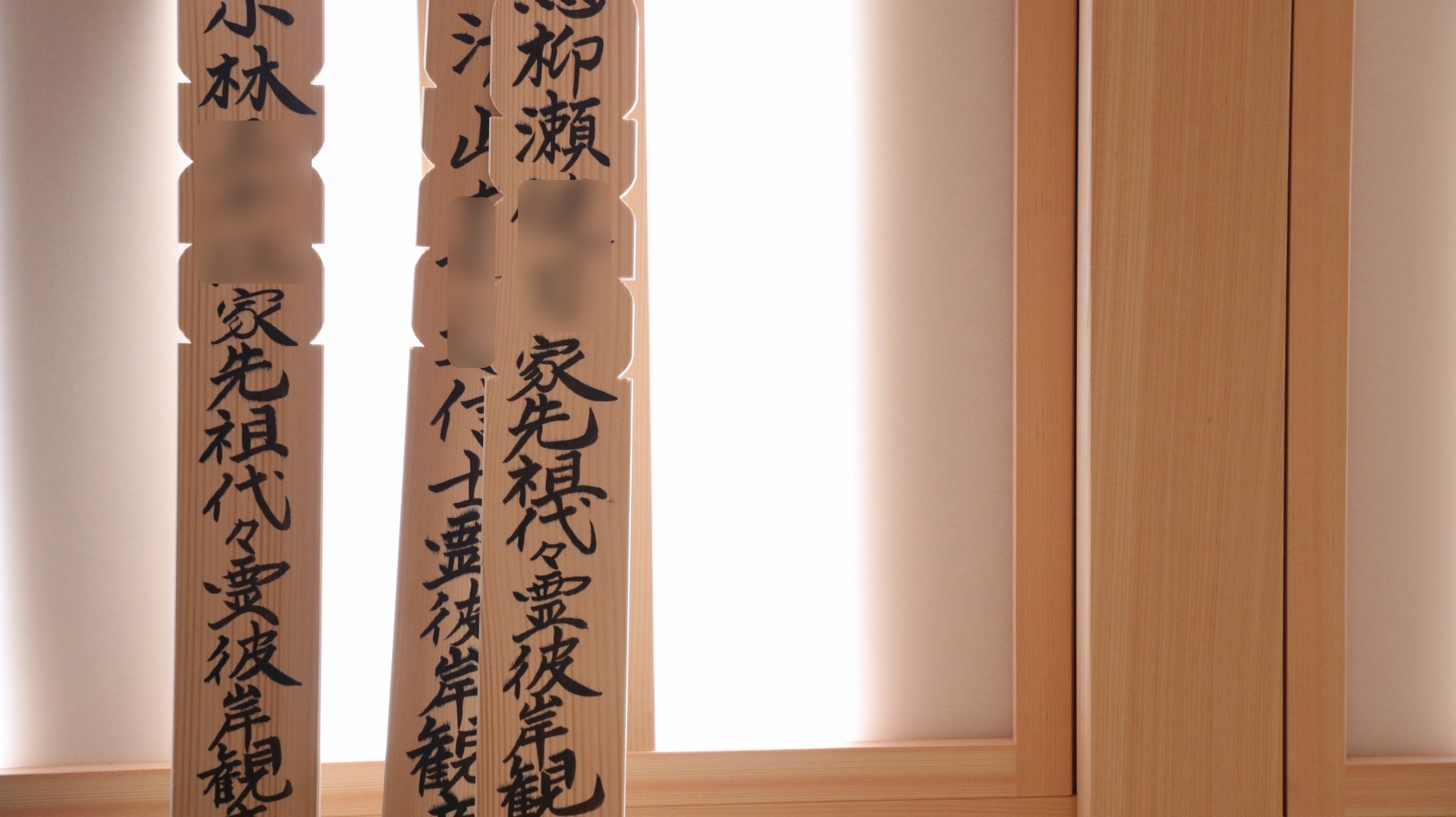
涅槃会の日
南伝仏教では
降誕会・成道会・涅槃会が
同じ月の同じ日に起こったとされ
4月(または5月)の
ウェーサーカ月の満月を中心にして
ウェーサク祭が行われています
日本では
涅槃会は 陰暦2月15日
とされてきましたが
明治時代に
太陽暦が採用されたこともあって
太陽暦の2月15日に
涅槃会が行う寺院が多くなっています
※陰暦で行われているお寺もあります
涅槃会
涅槃会が有名なお寺を
いくつか上げます
- 金剛峯寺「国宝の涅槃図」
- 東福寺 「猫が描かれている涅槃図」
- 泉涌寺 「日本最大の涅槃図」
- 西陣の本法寺「長谷川等伯の涅槃図」など
